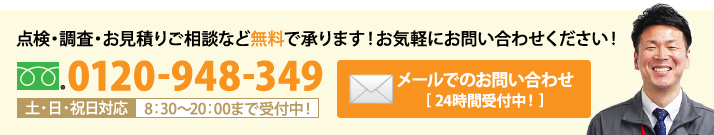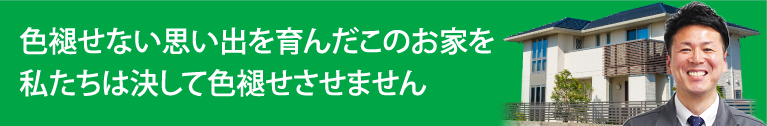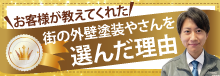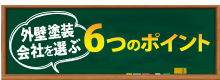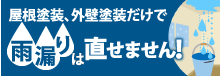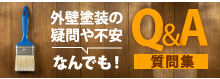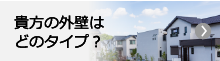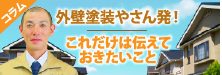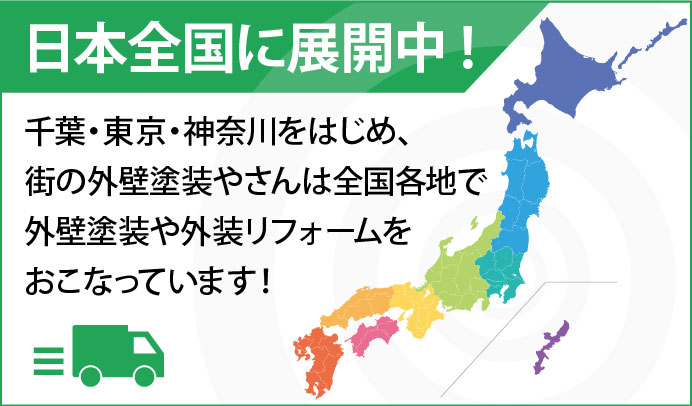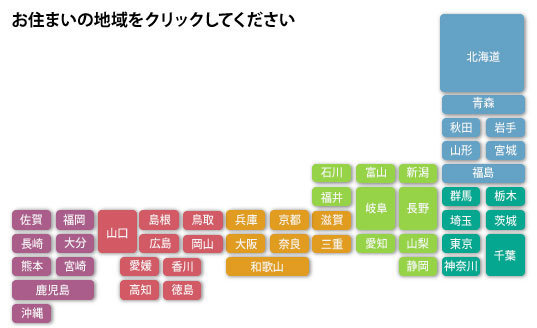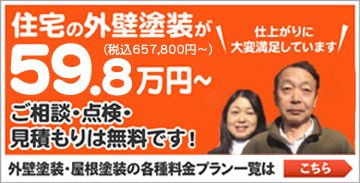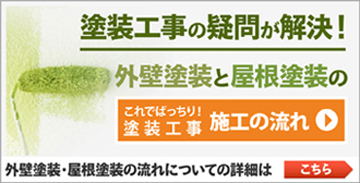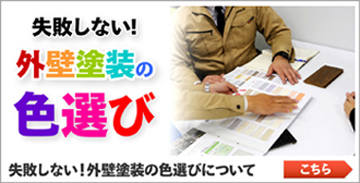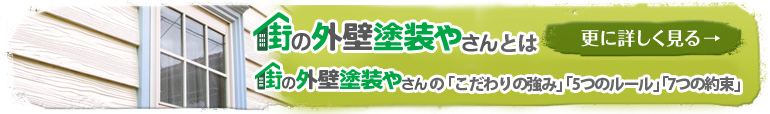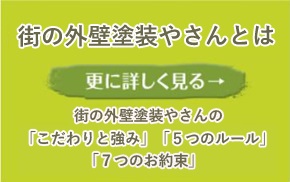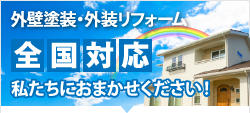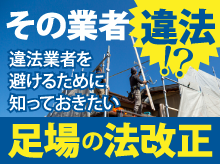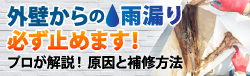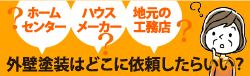軒樋取付と付帯塗装の密接な関係とは
昨日はあいにくの雨模様で工事はお休みとなりました。
本日は付帯塗装工事の続きと雨樋取付工事の様子をお届けします。
2日前は戸袋にサイディングのカバー工法でお色直しをしましたが、今日はどんな工事になるのでしょうか?


まずは付帯塗装の様子です。
綺麗に仕上がっていますが、私は職人さんでは無いので塗装に関して悩みがありました。
塗装をすると刷毛跡が残ってしまうのですが、どうしてそんなに綺麗に塗れるのですか?
聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥のごとく、解らないことは聞いていきます。
こういう小さな積み重ねがお客様に説明する際に役立つと思っています。
職人さんごとに経験値の差も実績も違いますから答えも色々あると思います。
一般の人は悪い所だけ塗ろうとするから刷毛の跡が付いてしまう。
個所じゃなくて面で仕上げることを意識すれば良いんだよ。
思い切りも時には大事なんだよ。
確かに悪い所だけ塗ってることが刷毛跡が付く要素だったのかと改めて思いましたね。
そんな職人さんの刷毛の動きを写真に収めました。確かに右から左へ刷毛が動いています。

次に雨戸周りを見ていきたいと思います。
こちらのお宅は雨戸枠が木製で、塗装も行います。
そこでよく相談があるのが…
雨戸が全然動かなくなってしまった!
というご相談が多いのです。
カッターを入れて雨戸枠と雨戸自体が塗装のくっつきを無くしてあげることが、私の体験上多かったことです。
これだと折角綺麗になった塗装がカッターで剥がれてしまうなぁと思うこともあります。
ですが、高齢者の方が多くなってきた日本では、塗料が接着剤の代わりをして動かそうにも動かないということが、より多くなると予想します。
動かそうとしてもかなりチカラが入りますからケガだけはお気を付けください。
日本の問題はさて置き、こういう所も職人さんが気を利かせて薄目に仕上げたりしますし、動作確認もしますのでご安心ください。
雨の対策は新しい雨樋が頑張ってくれます!


こちらは雨樋取付工事の様子です。
雨樋を新しくする際に支持金具(取付金具)も新しくしていきます。
塗装職人さんが塗った鼻隠しの部分に、金具が取り付けられていきます。
雨水を流すには必要な水勾配も取り、強風にも負けないようにしっかり止めていきます。


取付が終わった面の軒樋です。
集水器も雨水を竪樋に流す働き者ですが、近所に木が茂っていたりすると落ち葉が詰まってしまいます。
特に笹の葉が多い所だと、詰まって流れない雨水が逆流して思わぬ雨漏れを呼んだりして大変なことになります。
雨樋への落ち葉はポリネットと呼ばれるネットがありますので対策もできたりします。笹の葉が入らない網目の大きさを選ぶことが良いかもしれません。

竪樋もでんでん(支持金具)を取付けて交換完了です。
こちらも詰まりをおこしているお宅をよく拝見します。
私が今まで見てきた中で詰まっていたベスト3です。
①洗濯バサミ
②はりがね類
③埃(泥)や髪の毛、衣類の綿
ベランダ下にある軒樋から竪樋に流れる際に引っかかってしまう。さらに詰まりが重なっていくといった悪循環。
ゴミ取りネット等を活用し、雨の被害を最小限にしていきましょう。
ただ危険も伴いますので、街の外壁塗装やさんにも相談してみてください。チカラになりますよ!

最後になりますが、もう一度画像を載せますね。
これは一見なんて事の無い画像ですが、工事を進める際の注意点があるのです。
それは、
破風板、鼻隠しが濡れていないと雨樋が取り付けられないのです。
雨が降ったおかげで、鼻隠しが濡れないということがあったとしてもこれは困ります。
職人さんの予定もずれてしまいます…
ですが、職人さん達が連携して塗装~乾燥~雨樋取付ができるようにして頂きました。私はもっとしっかりしないといけません。
雨樋を先につけて、綺麗になった雨樋がペンキで汚れたり、塗れる所だけ塗って仕上がりが雑なんてことがあれば、ごめんなさいでは済まされません。
小さいローラーもありますが、仕上げ屋としての念持として避けたいところ。
どんなことでも段取りがありますから、段取りの重要性を更に肝に銘じました。
街の外壁塗装やさん狭山・所沢店では、仕上げ屋の念持をもってお客様に解りやすい外壁塗装工事のご説明をしております。
皆様の困ったをご相談ください。お待ちしております。
ご拝読ありがとうございました。
●前回のブログはこちら(内部リンクです)
記事内に記載されている金額は2019年10月20日時点での費用となります。
街の外壁塗装やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。
外壁塗装、屋根塗装、外壁・屋根塗装、ベランダ防水の料金プランはそれぞれのリンクからご確認いただけます。