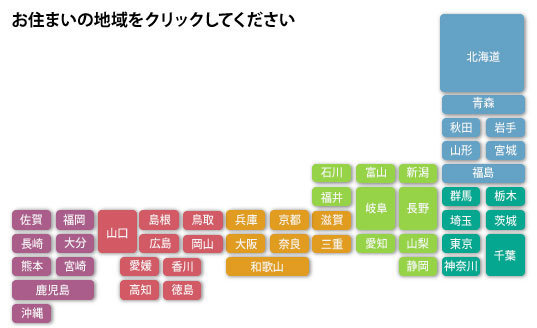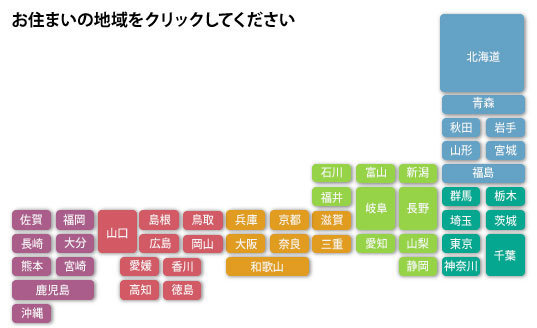昨日開放廊下の床、下地処理をブログにてお届け致しました。今日はその続き。上の写真は開放廊下の下地をカチオン系フィラーで平滑にした画像です。仕上げは長尺シートを上に貼ります。開放廊下の仕上げは他に、特殊な機械で超速乾の防水(吹き付け)、塗床(塗膜防水・防塵塗装)と複数あります。超速乾の防水材はバルコニーには良いと思います。理由としては雨が吹き込む可能性があるからです。今回の開放廊下の床は防水性能は、ほとんど必要ありません。防塵塗装した場合を考えると、入居者様の通行があるため、半分、半分塗るというかなり手間のかかる仕事となります。
防水性能が必要なく、意匠性の向上を考慮した場合は、床は長尺シートが有効だと考えられます。今回のように下地処理を平滑にさえしておけば、貼るのは楽チン。柄も豊富でオーナー様のニーズにもお答えする事が出来ます。

↑平場は長尺シートを貼り、側溝部分はウレタン防水で仕上げます。平場同様にシートを貼れば良いじゃないかとお考えの方もおられると思いますが、わずか15㎝程度の幅に厚みのあるシートを貼ると、シートが浮いてしまう可能性があります。また立ち上がりは直角に立上ってますので、シートが折れてしまいます。そんな理由から厚みのあるウレタン塗膜防水が有効となります。
今後もし開放廊下に水が浸入しても、平場は長尺シートでカバーしてくれ、余剰水分は側溝へと流れます。この仕組みだと今後雨が降りこんでも雨漏りの心配はありませんから安心出来ます。
前置きが長くなりましたが、上の画像は平場同様にカチオン系フィラーを防水屋さんが塗っています。水が溜まる部分には大目に塗布し水が溜まらないよう、また水の流が良くなるように下地を調整します。また微細なクラック(ひび割れ)にもカチオン系フィラーを入れる事で、上塗りした時に塗膜が痩せないようにしています。
お客様やオーナー様は最終仕上げに目がいきがちですが、一番大事な事は下地をどのように作るかが、仕上げに大きく差が出るという事をご承知おき頂ければと思います。
こうした目に見えない部分に価値があるという事です。
財産価値を維持していくには高級塗料も必要ですが、まずは下地をどのように作るかが、建物長持ちのポイントです。
ではまた明日!(^^)!
記事内に記載されている金額は2018年12月17日時点での費用となります。
街の外壁塗装やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。
外壁塗装、
屋根塗装、
外壁・屋根塗装、
ベランダ防水の料金プランはそれぞれのリンクからご確認いただけます。